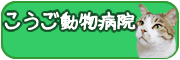未分類
チューイは3泊4日、ももたろうは日帰りでした。
という事で、まずはチューイから!


多摩センターにあるクロスガーデンのコーヒーショップでランチタイムです。
犬も人もよく通るのでこういうのは社会化トレーニングに最適ですね~♪
何事が起こっても平常心でいられるチューイ。
もし乱れても、すぐに平常心に戻れることが重要。


動物病院のしつけ教室に参加したチューイ。
場所が変われば犬の反応は変わります。
ややビビり気味のチューイですが、繰り返せば慣れていくでしょう。


ももたろう君が合流~♪
ここは、御岳渓谷です。
ラフティングしている人が結構いましたよ。


そばにある御岳山に登りました!
頂上は900m以上あるので気合入れて登ろう~!

御嶽神社に到着!
何回登っても達成感ありますな。
犬達の潜在能力はすごいのです。

私はかなり疲れたのですが、犬達は余力ありという感じです。
運動欲求満たすのは大変ですね。

ここで、ももたろうは帰宅。
リフレッシュできたなら幸いです♪

再び、チューイのみです。
ここは立川の若葉モール。


チューイは本当に大人しくていい子。
でもよ~しよしと撫でてやると、嬉しくて「ウォー!キャオー!」と歌うように声が出る、面白い性格です。
これに対して、吠えるな!などと言うのはちょっと違うでしょう。

犬はそれぞれ性格が違います。
自分の犬の性格・性質を掴むことが飼い主さんの最初の一歩でしょう。
見当違いなしつけをしない為にもね・・・!
ドッグトレーニングアクアに縁がある犬や一緒に学ぶ仲間犬をご紹介していきます。
随時、更新していきますので時々ご覧になって下さいね♪
和して同ぜず。
調和と同調の差ですが、これは一体何が違うのでしょうか?
簡単に言うと、
人と仲良くするのは良いけど、何の考えもなくむやみに仲良くするのは間違い、ということ。
感性によってこの違いを見分け、聞き分け、嗅ぎ分けましょう!
視覚、聴覚、嗅覚は、その刺激となる対象と少し距離があるもの。
しかし、味覚と触覚は身体と直に接触するので(味わう、触れ合う)、より刺激的であり、ぶっつけ本番的なものになります。
実際に食べてみて味に異変を感じたり、実際に触れた時に違和感を感じるわけですから。
やってみなけりゃ本当の所は分からないのです・・・!(しつけもね)
感性とは、この五感を通じて「何かを感じ取る力」のこと。
感性が鋭いのは傷つきやすさでもあります。(感じ取り過ぎてしまう)
感性が鈍いのは傷つけやすさでもあります。(相手の気持ちを感じ取れないこともある)
例えば、
犬を叱ったらその後いくら呼んでも来なくなったとします。
何で来ないのかさっぱり分からない・・・というのは鈍すぎる人ですが、
叱ったから来なくなったのね、と落ち込んでしまうのは鋭すぎる人です。
気付いてるけどあまり気にしないというバランスが大切ですね。
全て理解した上で対応策を工夫すればよし。
こういう受動的なことは感性として理解されやすいのですが、犬のしつけで真に大切なのは能動的な感性です。
いわゆる第六感ですね。犬の気持ち(本質)を瞬時に掴む!
これは理屈を超えますのでネットや本でいくら勉強しても残念ながら身に付きません。
犬のしつけで重要なのは、まず犬の気持ちを感じ取ってやること。
そして、どうやって犬に自分の気持ちを伝えるのか?ということ。これは表現力とも言えます。
その方法や度合い、頻度、間隔、角度、抑揚、タイミングなどの工夫です。
犬に対して、褒めるのか、叱るのか、無視するのか、何を一体どうすればいいのか??
表現の形は無限にあるけれど、犬に伝わるやり方は限られているはずです。
ぜひ、自分の犬の性質に合ったしつけ方法を見つけてあげましょう。主役はあくまで犬ですから。
私のしつけスタイルはこれだ!と決めた途端に、感性は錆びついてくるでしょう。
常に向上を目指し疑問を持ち続けることが、感性に磨きをかけるのです。
あなたが犬からどんなことを感じて、しつけではどんな工夫をしたか?全部書き出してみるのも価値ある行為となるでしょう♪
皆さんの健闘を祈ります!
次回から新シリーズ「アクアの学び舎」が始まりますのでご期待下さいね♪
「手前どもは」
と言うと商人が自分のことをさす言葉として使っているシーンが思い浮かびます。
番頭さんがお客さんにへりくだっていて物腰が柔らかな感じ。
「てめえ」
と言うと相手をさす言葉であり、喧嘩腰でピリピリしている感じがします。
「お手前拝見」
と言うと相手の技量を測る意味になりますね。
さて、犬のお手前とは?
それは、パフォーマンス的な技をいくつできるかではなく、実力があるかどうかが大事です。
家ではオスワリできるが外ではできない・・・ご飯の時はとてもお利口だけど・・・
これはパフォーマンス的であり、本当の意味でしつけができているとは言い難いですね。
家だとボールを持ってくることができるけど外ではできない、周りに犬がいるとできない、というのも同じです。
気分が乗ればやるというのでは不十分なのです。
気分が乗らなくても確実にやる、これは練習と忍耐の果てに獲得できる能力です。
ボールを投げても「待て」の指示があればちゃんと待つのがしつけ。
ハードルがあるから飛ぶのではなく、「飛べ」の指示があるから飛ぶのがしつけ。
「商い」は「飽きない」ことがコツと言います。
派手にドーンッと技を披露するのではなく、(一発当てて大儲けは狙わない)
本腰入れて地味にコツコツと飽きることなく練習を重ねることが犬のお手前を上げることに繋がるのですよ♪
距離感、これが難しいんですよね・・・!
離れすぎててもダメですし、近づきすぎても具合が悪くなります。
例えば、人と話す時の距離感とか、前の車との距離感とか。
「ちょうどよい」とは神経使うもの。
そして優しくて気を遣う人ほど、神経すり減らして疲れてしまうものですね。
逆に無神経な人は距離感などお構いなし。
でも、そもそもの感覚自体が全然違う場合もあります。
例えば、外国人と日本人は礼儀作法や時間感覚も違いますね。
挨拶でハグするのは日本人には無い感覚ですし、待ち合わせ時間に何分まで遅れるのは許せるか?というのは国によってかなり違うでしょう。
そういう感覚の違いは人間同士で・す・ら・あります!
相手が犬なら尚更でしょう。
ですから、あまり自分の感覚で犬のことを考え過ぎない方が良いということです。
距離感とは心の隔たりですから、相手の反応を客観的に見て、自分の感覚を疑うのも時には大事・・・!
犬との実生活では呼べば必ず聞こえて応じられる距離がちょうどよいと思います。
至近距離すぎると呼ぶ(求める)必要もなくなりますし、遠距離すぎても声が届かなくなるので要注意。
犬を呼んでも反応がない、犬の要求に応じないと吠えたり咬んだりされる・・・
これは犬との距離が近すぎたり、遠すぎたりしてるのかもしれません。
心の隔たりを埋めるのは犬と一緒にいる時間です。(相手に優しくする)
心の隔たりが無くなってしまっているならば一線引き、あえて犬と離れる時間を作ること。(一日一回ハウス入れる)
紙クズをゴミ箱へ放り投げるが如く、犬との距離感を磨き、犬の必要としていることを見抜くことですよ♪
常識とは説明するのが意外と難しい言葉です。
Aさんにとっての常識とBさんにとっての常識は違っていることも多々ありますから。
例えば、理想の男性像や女性像が人それぞれで違うように。
男らしさ、女らしさと言う、この「らしさ」はその人の常識が言わせているものなのです。
辞書で調べると常識とは一般社会人が共通で持つべき知識や意見とあります。何とも分かりづらい・・・
私の意見ですが、常識は「社会に出ている人」によって違うものだけど、根本的な「人」としての常識は同じだよ、と。(人を傷つけてはいけない等)
「犬に対して」の常識も人それぞれで違いますね。良い、悪いは抜きにして。
でも根本的な「犬」に対しての常識は同じです。猫のことを犬とは呼ばない。猫は吠えないが犬は吠えるとか。
では、「犬自身」の常識とは何でしょうか?
現代の犬に人間との関わりを一切断て、というのは不可能です。ゆりかごから墓場までピッタリと人間がついてます。
そして人間との関わり方は犬それぞれです。従順な子もいれば、反逆児もいます。良い、悪いは抜きにして。
しかし、常識のない犬だなぁとはあまり言われませんね。
私達は、あいつは常識ないなぁとか簡単に言ってしまいがちですが・・・!(気を付けようっと)
根本的な「犬自身」の常識とは、
生きること、それだけだと思います。
食べ物に興味持つのも生きる為だし、人に従順にふるまうのも生きる為です。(逆パターンもあります・・・)
もし犬が人を咬んで傷つけてしまったら、我々の常識だとあり得ない行為だ!となるのですが、
犬の常識は生きることなので、生きる為に咬んだのならばあり得る行為なのです。(これは納得不能なので油断禁物)
だからこそ、
お互いを知ろうとすることで常識のすりあわせをして、犬の常識を人の常識まで引き上げておかないといけません。
要するに、勉強して(P)、しつけして(D)、検証して(C)、可愛がって(A)、色々やって咬まない犬にしてあげましょう!
威嚇して吠えるのも攻撃の一種なのでこれも直してあげましょう!ということ。
犬のPDCAサイクルですね。勉強して実行、チェックして改善、そして油断はしない。これを繰り返して犬とのより良い生活を♪